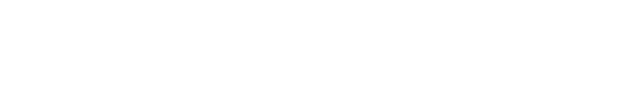HPV(子宮頸がん)ワクチンについて
子宮頸がんは20代からの若い女性に増えています
・子宮頸がんには、日本では毎年約1.1万人の女性がかかり、毎年約2,900人の女性が亡くなります。子供を残して亡くなるお母さんのケースが多いことから、「マザーキラー」とも呼ばれています。
・患者さんは20代から増え始め、30代までにがんの治療で子宮を失う(妊娠できなくなる)人も、1年間に約1,000人います。
*子宮頸がんは若い人がかかる病気に変化しています。(国立がん研究センターがん情報サービスより)
*子宮頸がんになる人も、それにより亡くなる人も、共に増えています。(日本産科婦人科学会ホームページより)
子宮頸がんはヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染で生じます
・HPVには、女性の多くが一生に一度は感染します。感染は主に性的接触によって起こり、一生のうちに何度も起こりえます。感染してもほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人ではがんになります。
HPVワクチンの接種とキャッチアップ接種について
・日本では、小学校6年~高校1年相当の女の子を対象に、子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチン(HPVワクチン)の公費(無料)接種を提供しています。
・令和5年4月1日より、これまでの2価・4価に加え、9価のHPVワクチンを公費(無料)で受けることができるようになりました。
・また、これまで接種の機会を逃し、過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方も、令和7年3月31日までの間は同様に公費(無料)でHPVワクチンを接種できます。この救済措置をキャッチアップ接種と呼びます。
・キャッチアップ接種は同じ種類のワクチンを打つのが原則ですが、厚生労働省は、3回接種のうち1回目又は2回目までを2価又は4価ワクチンを接種している方が、9価ワクチンで残りの回数を接種すること(交互接種)について、接種者が強く希望する場合は医師と相談の上で実施できるとしています。
・2価・4価・9価のワクチンのそれぞれの違いはワクチンがカバーするウイルスの種類(型)の違いです。これまでの2価(サーバリックス)・4価(ガーダシル)ワクチンがおおむねHPVのうち、50~70%を防ぐのに対し、9価(シルガード9)ワクチンは80~90%を防ぎます。
HPVワクチン接種の公費助成対象者と接種スケジュールについて
| 公費助成対象者(無料):横浜市に住民登録がある方 | ||||
| 性別 | 対象年齢 | シルガード9(9価)の接種回数 |
ガーダシル(4価)の接種回数 |
標準的な接種間隔 |
|
女性
|
①初回接種時 11歳以上~15歳未満 |
2回 | 3回 |
初回接種の6か月後に追加接種 |
|
②初回接種時 15歳以上~16歳未満 |
3回 | 初回接種の2か月後と6か月後に追加接種 | ||
|
③キャッチアップ接種 16歳以上~27歳未満 |
3回 | 3回 | 2回目の接種は初回接種から最低2か月以上、3回目の接種は2回目から最低4か月以上間隔をおく | |
|
①②小学校6年生~高校1年生に相当する年齢の女性:誕生日が2007年(平成19年)4月2日~2012年(平成24年)4月1日の方 ③誕生日が1997年(平成9年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日の女性(過去にHPVワクチン接種を合計3回受けていない方を対象に2025年(令和7年)3月末までの救済措置となります) |
||||
*接種を希望される方は当院までお問い合わせの上で、ご予約をお願いします。
*接種当日は確認のため、母子手帳、横浜市より郵送される予診票、保険証をご持参ください。
*予防接種法上、16 歳未満の方はワクチンの接種にあたって保護者の同意が必要となりますので一緒にお越しください。
HPVワクチンのリスクについて
| 発生頻度 | 9価ワクチン(シルガード9) | 4価ワクチン(ガーダシル) |
|
50%以上 |
接種した部位の疼痛 | 接種した部位の疼痛 |
|
10~50%未満 |
接種した部位の腫脹・紅斑、頭痛 | 接種した部位の腫脹・紅斑 |
|
1~10%未満 |
接種した部位の痒み・内出血、浮動性めまい、悪心、下痢、発熱、疲労など | 接種した部位の痒み、頭痛、発熱 |
|
1%未満 |
接種した部位の出血・血腫・硬結、嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、倦怠感など | 接種した部位の出血・血硬結・不快感、下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、倦怠感など |
|
頻度不明 |
感覚鈍麻、失神、四肢痛など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など |
|
シルガード9添付文書(第1版)より改編 |
ガーダシル添付文書(第2版)より改編 |
|
*HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。また、まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。
*シルガード9接種後に生じた症状として報告があったのは接種1万人あたり約8人です。このうち、重篤と判断された人は接種1万人あたり約7人です。
*サーバリックスまたはガーダシル接種後に生じた症状として報告があったのは接種1万人あたり約9人です。このうち、重篤と判断された人は接種1万人あたり約5人です。
よくあるご質問
Q:HPVワクチンを打つのは3回接種できる15歳になるまで待った方がいいですか?
A:HPVワクチンはシルガード9(9価ワクチン)であれば14歳までに接種開始された方は2回接種とされています。これは14歳までであれば2回の接種で十分効果があるため、3回ワクチンを打つ必要がなくなるからです。注射の回数も1回少なくて済むことから、14歳までの接種をお勧めいたします。
Q:いつからHPVワクチンの効果がありますか?
A:海外では1回接種でも効果が報告されています。一般的にワクチンの予防効果は2週間ほど経過してから、と考えられています。
Q:いろいろ忙しくて、規定通りにワクチンを打つことが難しいのですが?
A:シルガード9で2回接種を予定している場合、本来2回目は6か月後に打つ決まりですが、2回目を5か月後~12か月後までの間で打つことが可能です。ガーダシルの場合、本来2回目は2か月後、3回目は6ヶ月後に打つ決まりですが、2回目を1~2か月後までの間に、3回目を2回目接種してから3~4か月後までの間に打つことが可能です。
Q:2価あるいは4価のワクチンをすでに3回接種して終えていますが、あらためて9価のワクチンを打てますか?
A:現状では、2価あるいは4価ワクチンを3回接種した後で、9価ワクチンを接種することについては、安全性の検討がなされていないため、不可とされています。
Q:男性でもHPVワクチンを打てますか?
A:男性では9歳以上であれば、4価ワクチンであるガーダシルを女性と同様に6か月間で3回接種することが可能です。HPVワクチンは子宮頸がんや膣がんといった女性に特有の疾患のみならず、陰茎がん、肛門がん、中咽頭がんといった悪性腫瘍に加え、良性疾患である尖圭コンジローマのような性感染症の予防効果も認められています。ただし男性の場合、現在公費接種の対象ではなく、自費となります。当院の場合、ガーダシルは1回当たり16,500円(税込)の費用がかかります。
Q:30~50代の女性は、HPVワクチンを接種しても意味ないですか?
A:一般的に、性的接触の回数やパートナーが少ないほうがHPV感染のリスクは低いです。年齢に関わらず、性的接触が活発な方はHPVに感染するリスクを有していますので、HPVワクチンを接種する意義はあります。ただし公費接種の対象とはならず、自費となります。
Q:すでにHPVに感染してますが、それでもワクチンの効果はありますか?
A:HPVワクチンは感染を予防するためのワクチンなので、すでに感染したHPVを無くすことはできません。ですが、ハイリスクの型である16と18の双方のHPVに感染している方は少なく、また9価ワクチンはその他に31,33,45,52,58といったハイリスクの型も予防するため、自分が感染している以外の型を予防する目的でワクチンを接種する意義はあります。
Q:妊娠中(または)授乳中です。HPVワクチンを接種できますか?
A:添付文書上は妊娠中は接種の有益性が危険性を上回る場合、接種してもかまわないとされています。また、本人が妊娠に気づかずに接種を受けても母子のリスクは増えないとする研究結果もあります。ですが、接種を急ぐ必要もありません。授乳に関しては授乳の中止を検討するか、授乳を終えてから接種することが望ましいとされています。以上より、妊娠・授乳に関してはいずれも妊娠・授乳と双方共に終えてから接種開始/再開することをお勧めします。
Q:新型コロナワクチンを接種する場合の間隔はどのようにしたらよいですか?
A:新型コロナワクチンと子宮頸がんワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合には可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
Q:インフルエンザワクチンと子宮頸がんワクチンは同時に接種できますか?別々に打つ場合の間隔はどれくらいですか?
A:インフルエンザワクチンと子宮頸がんワクチンを同時に接種することは可能です。先にインフルエンザワクチンを打った場合、不活化ワクチンであるため、特に接種間隔に制限はありません。そのため、同日でも翌日でも接種は可能です。(これまで一般的には不活化ワクチン同士を接種する場合は6日以上間隔を空けるとされてきました)
Q:麻疹風疹ワクチンと子宮頸がんワクチンを同時に接種できますか?別々に打つ場合の間隔はどれくらいですか?
麻疹風疹ワクチンと子宮頸がんワクチンを同時に接種することは可能です。先に麻疹風疹ワクチンのような生ワクチン(麻疹・風疹・おたふくかぜ・BCG・黄熱ワクチンなど)の予防接種を受けた場合、同じ生ワクチン同士の接種は27日以上空ける必要がありますが、不活化ワクチンである子宮頸がんワクチンについては特に制限はありません。そのため、同日でも翌日でも接種は可能です。(これまで一般的には27日以上間隔を空けるとされてきました)
👉異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール(厚生労働省)